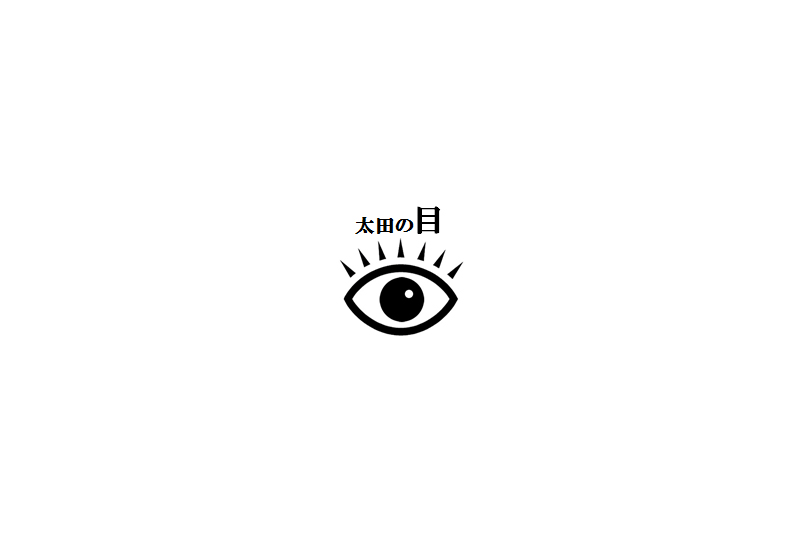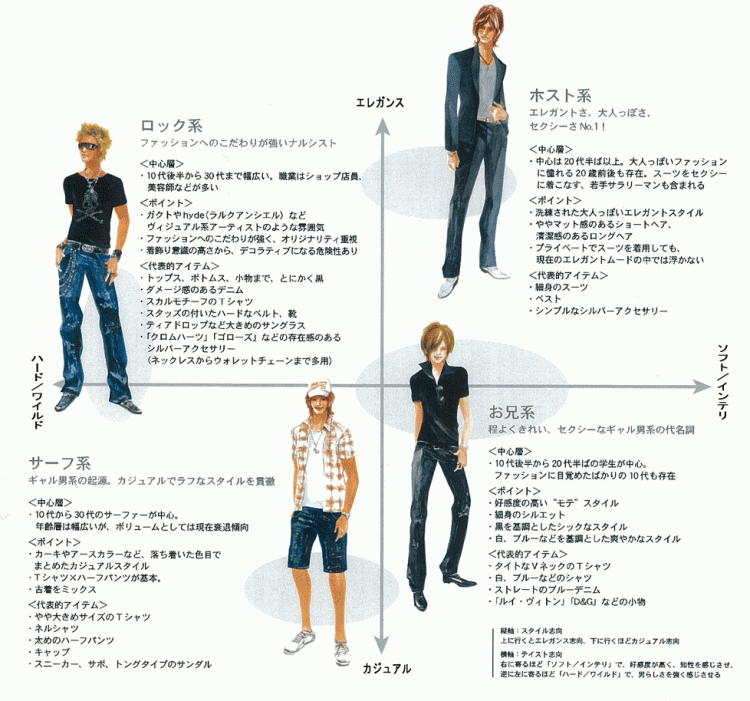■【第1期】
バブルファッション時代
平成元年( 1989)~平成3年( 1991)
平成元年(1989) はまだ、1986 年から始まったバブル景気真っ盛りだった。景気の高揚感とともに円高による輸入商品の割安感が伴い、インポートブランドブームがもたらされた。それまで、インポートブランドは富裕層だけが持つ特別な存在だったが、円高による海外旅行ブームと輸入価格の低下によって、一般庶民にも認知されるようになった。インポートブランドは海外で買う方が安いという理由で、ブランド購入目的の海外旅行という現象も起き、有名ブランドの本店では日本人の長い行列が出来、入店制限が起きるほどだった。中国人観光客による「爆買い」以前に、日本人は欧米で「爆買い」していたのである。また、国内ファッション市場では、レディースでは「ボディコンシャス」、メンズでは「ソフトスーツ」ブームが起きた。いわゆるバブル期のファッションの特徴として今でも語られるコーディネートである。
それと並行して、渋谷に集まる私立高校生や大学生を発信源にブームとなったのが、「渋カジ・キレカジ」だ。その象徴が「紺ブレブーム」( =金ボタンのネイビーブレザーを軸にしたコーディネート)。トラッドやブリティッシュに関係のないブランドまでが、この機を逃すまいと「紺ブレ」を作って売った。デザイナーやアパレル企業が発信するものではなく、ストリートから自然発生したトレンドが日本中に広がるという現象が、これを境に常態化していった。
この「渋カジ・キレカジ」ブームを支えていたのが、バイヤーのこだわりを打ち出してインポートを軸にセレクトされた商品を売る「セレクトショップ」で、以降、セレクトショップはこの当時高校生だった団塊ジュニア世代の支持を得ながら日本のファッションビジネスを支える主力業態へと成長していく。
■【第2期】
価格破壊と日本型SPAの時代
平成4年(1992)~平成9年(1997)
お祭り気分が嘘のように、景気は一気に後退局面へと向かっていく。それまで、景気が後退しても若者の消費には大きな影響を与えないだろうと言われていたが、時代の気分を捉える高感度のアンテナを備えた若者は不況も鋭く察知してしまう。ファッションもバブル時代の装飾性の高いものから、地味な「フレンチカジュアル」へと一変する。「フレンチカジュアル」はモノトーン中心で価格も手ごろ、着回しがきくという不況に強いファッションだったことがブームを加速する。
また、不況はビジネスモデルの変革も生んだ。これまでは、百貨店や専門店向けにシーズンごとに展示会を開き、そこで大まかな受注を取っていく方式が主流だったが、景気後退期に入り、販売数予測が立てにくくなったことで小売り側ではリスク回避による控えめな発注が多くなった。取引条件に関しても、「買い取り」では百貨店側の売れ残りリスクが大きく、一方で「委託販売」は返品によってアパレルの負担が大きい。これに対して、アパレルがシフトを切ったのは「卸型の百貨店ブランド」から「日本型SPA」への転換だ。その先駆けとなったのが、平成5年(1993) にデビューした株式会社ワールドの「OZOC(オゾック)」である。小売店とは消化仕入れ方式の契約を結び、自社が企画し、自社の販売員が売る。展示会での受注をやめ、期中の売れ筋を見ながらクイックに生産して、在庫をできるだけ減らす。百貨店側も売れ残りのリスクはない。「場所貸し」との批判をよそに、この方式は拡大していく。まさにこの日本型SPAは、不況期をWIN-WINで乗り切る手段として業界内に広がっていった。
日本型SPAの増加は駅ビルの進化ももたらした。DCブランド中心のファッションビルに対し、駅ビルは専門店チェーン中心のテナントミックスで、実用性はあっても、おしゃれさは今一つだった。それがアパレルのSPAブランド増加に伴い、テナントの選択肢が増加。駅ビルのトラフィック( 通行量)に目をつけたセレクトショップも、ルミネなどへの出店を行うようになった。トラフィックと感度という2つの武器を手にした駅ビルは、鉄道会社による駅の有効活用策とも相まって、ファッションの購入場所としてのポジションを築くようになる。
もともとDCブランドでSPA 的な展開を行ってきた株式会社ファイブフォックスは、郊外型SC(ショッピングセンター)での展開を開始する。平成5 年(1993) デビューの「コムサイズム」である。手頃な価格、ファミリーターゲット、ベビーカーでも入店できる店舗レイアウトに加え、郊外であってもモード性やトレンド性を維持したことが受けた。当時の郊外型SCは「ららぽーとTOKYO-BAY」や「つかしん」といった一部の大型SCを除き、GMS(総合スーパー)をキーテナントとし、それを補完する少数の専門店や飲食店が付帯したものが中心だった。その後、平成4 年(1992)に「イオン柏ショッピングセンター( 現在:イオンモールつがる柏)」がオープンし、本格的なモール型SCの時代に突入していく。これが郊外型SC向けブランドの開発を加速させた。この時代、都心から郊外まで日本型SPAが主力業態となっていった。
■【まとめ】
景気に翻弄されつつも日本型SPAというビジネスモデルで乗り切った平成前期
バブル期以前にあったDCブランドブーム、バブルによるインポートブランドブーム、その後の「渋カジ・キレカジ」ブーム。平成前期のファッションの主導権は常に10 ~ 20 代にあった。都市部の路面店と駅ビル・ファッションビルは10 ~ 20 代を中心としたビジネスモデルを確立させた。その結果、百貨店はミセスとシニア層、郊外はファミリーというように年齢層による棲み分けが明確になったのも平成前期である。また、不況期に一気に拡大した日本型SPAは、ブランドのコンセプトや個性よりも、短期的な売れ筋商品や効率よく生産できる商品が優先された。現在懸念されているブランドの同質化はこのころに始まっていたといっていい。さらに、SPA業態の一般化により、日本のファッションビジネスの中心軸は「企画・製造・卸」というアパレルビジネスから、「企画・製造・販売」という小売りビジネスへと大きく変貌していった時代でもあった。
この激動によって消費者のセンスや選択眼も磨かれたし、それに対応する選択肢も増えた。バブル期でインポートなどの選択肢が身近になり、バブル崩壊でお金をかけずにファッションを楽しむ方法を学んだ。さらに、郊外型SCの進化によって、都市と地方の格差も縮まった。
これらのことから、平成前期は良い面、悪い面を含めて現在のファッションビジネスの外枠が形成された時代だったといえる。
<< 激動の平成ファッションビジネス史年表 >>